病院の空調方式を選定するのは容易なことではありません。特に、医療施設は他の建物と異なり、患者の快適性、エネルギー効率、そして感染防止対策などが必要です。
10年の設備設計経験を経てから20年以上病院施設管理に従事している現役の施設管理者が、空調方式の選択に悩む方へ実践的なアドバイスを提供します。
この記事では、医療施設における空調方式の特徴や選択基準についてわかりやすく解説し、長期的なコスト管理や安全性の確保、そしてエネルギー効率を最大化する方法を探ります。
このガイドを通じて、最適な空調方式を選定するための判断力が高まり、将来のトラブルを未然に防げるようになるはずです。
病院施設の複雑なニーズに合致した空調方式を選択するためのヒントを、この記事で掴んでください。

今病院の空調設備の計画してるんですけど、病院って色んな部門があって空調設計って難しいですね~

そう!事務ビルやホテルとは違って専門的な知識が必要やし、設計にはそれなりの経験が必要やな!
1. 病院空調の選定における基本方針
病院の空調設備は、多様な用途と厳しい衛生管理基準を満たす必要があり、他の建物とは異なる配慮が求められます。本記事では、都市部に立地する延べ床面積10,000㎡、200床規模の病院を想定し、以下の観点から適切な空調方式の選定方法を検討します。
1.1 病院空調の重要性
感染管理と清浄度維持:感染管理のため、HCU(高度治療室)や手術室には高性能フィルターを備えた空調設備が不可欠です。また現在は発熱外来や発熱病棟などエリア分けを行い、陰圧室を設けて院内感染を防止する対策も必要になってきています。
快適な温湿度管理:患者や医療スタッフの快適性を重視し、病室ごとの温度調整や静音性も重要なポイントです。
エネルギー効率とコスト管理:高効率であることに加え、長期的な運用コストを抑えられる方式が求められます。
1.2 病院の空調方式の選定で考慮するべき条件
エネルギー源の選定: 電力、ガス、または電気+ガスのハイブリッド方式について、地域のエネルギー供給状況や料金設定を踏まえて決定します。後ほど触れますが都市ガスが供給されている地域においては電気+ガスのハイブリッド方式が最適な選択といえます。
維持管理の難易度とコスト: メンテナンス頻度や修理コスト、設備の耐用年数も重要です。将来的に更新する時に工事し易いような設計に心がける必要があります。
法律・規制の遵守: フロン排出抑制法など、空調設備に関する環境規制に適合する必要があります。

感染症対策は本当に重要ですね。

最近は陰圧室を設けて院内感染を防止する対策が必須やね!

次は具体的な空調方式の比較を考えよか!
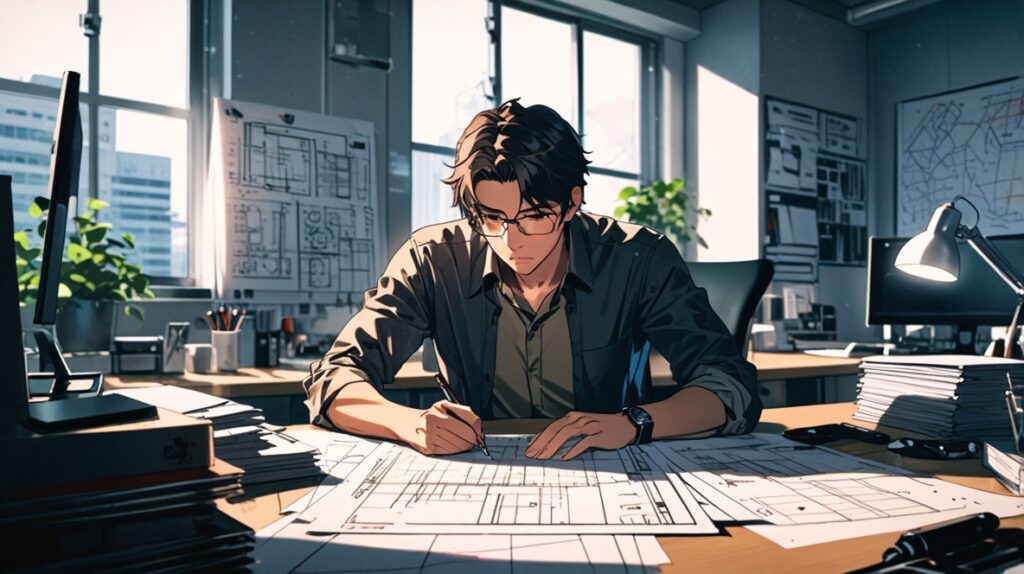
2. 空調方式の比較検討
2.1 電気式空調設備の利点と欠点
<メリット>
- エネルギー効率の高さ: 電気を使用するヒートポンプ方式やビルマルチエアコンは、少ないエネルギーで冷暖房が可能です。これは主にヒートポンプが外気の熱エネルギーを利用し、効率的に室内を冷却・加熱するためです。特に部分負荷運転に優れ、季節や利用者の変動に対応しやすく、病院のように24時間体制で稼働する施設に向いています。
- 安定した冷暖房供給: 電力供給の信頼性が高く、温度管理が重要な病室や検査室、手術室での連続運転に適しています。特にビルマルチエアコンは各部屋ごとの温度調節が可能で、患者ごとの快適な環境を提供できます。
- 柔軟性のある設計: 病院内のエリアごとに個別の制御を行いやすく、使用者や利用状況に応じた最適な温度調整が可能です。
<デメリット>
- 電力コストの増加リスク: 電気料金はガスと比べて変動が大きく、ピークシーズンには高騰する可能性があります。特に夏季や冬季に冷暖房需要が集中するとランニングコストが増加し、病院全体のエネルギー費用が膨らむリスクがあります。またデマンド値(最大電力)により基本料気が決定されるため、ピーク電力が大きくベース電力が小さい(負荷率が悪い)施設ですとランニングコストが大きくなってしまいます。
- 停電リスク: 電気のみをエネルギー源とするため、停電が発生すると一時的に空調が停止し、予備電源の確保が必要となる場合もあります。
2.2 ガス式空調設備の利点と欠点
<メリット>
- 長期的な運用コストの抑制: 主にガスを使用するため、電気代の変動リスクを抑え、安定した運用コストを実現できます。ガス料金は比較的安定していることが多く、特に冬季などエネルギー需要が高まる季節にもランニングコストを抑えやすいです。
- エネルギーセキュリティ: 停電が発生してもガスを使用するシステムは引き続き動作できるため、非常時のバックアップとして機能します。病院のような緊急性が高い施設では、ガスを併用することで、空調設備が安定的に稼働できる環境を確保できます。
<デメリット>
- 初期導入コストの高さ: ガス式空調設備は導入コストが高く、また施設内でのガス配管工事が必要となるため、設計段階で予算への影響が大きくなります。
- メンテナンスの専門性: ガスを使用する設備は、定期的な点検や保守が求められ、特定の技術者の確保が必要です。また、設備自体が複雑であるため、長期的には運用計画やメンテナンスのサポート体制を整えることが課題となります。
2.3 電気+ガスハイブリッド方式
<メリット>
- 安定供給と運用コストの両立: 電気とガスの二重のエネルギー供給が可能なため、電力ピークの負荷をガスに分散させることで電力消費を抑制しつつ、安定した空調を実現できます。都市部ではエネルギー供給の信頼性を高める手段として有効です。
- ピークシフト対応: 電気需要のピーク時にガスへ切り替えることで、病院全体のエネルギー消費を抑え、特に夏季・冬季の電力ピーク時の運用コストを安定化させることが可能です。
<デメリット>
- 複雑な運用管理: 電気とガスの併用によるシステムは構成が複雑になり、管理や運用が難しくなります。専門的な設計と計画が導入時に必要であり、施設管理者には高度な知識が求められます。
- 導入費用の増加: 二重システムのため、初期導入コストが高くなり、コスト面での調整が求められます。
2.4 ビルマルチエアコン方式
<メリット>
- 細やかな温度調整: 各部屋ごとに温度設定が可能なため、病室や診察室など、用途に応じて適切な空調管理ができます。患者やスタッフごとの快適性を高めることが可能で、特に病院のような個別環境が重要な施設には向いています。
- 部分負荷運転の優位性: ビルマルチエアコン方式は、使用していない部屋の空調を停止したり、必要なエリアだけを効率的に冷暖房することができるため、省エネ効果も期待できます。
<デメリット>
- スペースの確保: 外部ユニットが複数必要になる場合があり、設置スペースの確保が病院施設の構造上の制限を受けやすいです。
2.5 ファンコイル方式(電気式空冷ヒートポンプチラー)
<メリット>
空調を安定して供給することができ、エネルギー効率も比較的高いです。特に設置や運用のシンプルさが求められる病院では、信頼性のある冷暖房が可能です。また導入費用も低く抑えることが出来ます。
<デメリット>
電力コストが高くなる可能性があり、ピーク時の負荷対策が求められます。また、チラーの設置場所や騒音対策が必要な場合もあります。
2.6ファンコイル方式(ガス吸収式冷温水発生器・ガスヒートポンプチラー)
<メリット>
ガスを主要エネルギー源とするため、運用コストが比較的安定しやすく、電力消費を抑えた空調運用が可能です。特に電力消費が多い施設で、運用コスト削減を重視する場合に適しています。
<デメリット>
専門的なメンテナンスが必要で、技術者の確保やサポート体制の整備が求められます。また、設置スペースや排ガスの処理にも注意が必要です。

すべてのシステムにメリットとデメリットがあってさらに混乱してきましたけど…

大丈夫!もう少し!次は各エリアに応じた最適な空調方式を考えてみよか!

ホンマにもう少しですか?それなら頑張りますけど…

3. 病院の各エリアに応じた空調方式の提案
3.1 入院病棟
個別空調方式またはビルマルチエアコンの導入: 患者の快適性を最優先とするため、各病室ごとに温度を調整可能な個別空調方式が推奨されます。各部屋の使用状況に合わせた柔軟な運転が可能です。個別エアコンを導入する場合は、室外機置場の確保が必要です。病室のすぐそばにバルコニーなどのスペースがあれば採用しやすい方式ですね。個別の室外機置場が確保しずらい施設はビルマルチエアコンの導入を検討しましょう。
3.2 手術室・HCU(高度治療室)
高度な清浄度維持機能が必要: 手術室やHCUは、感染防止のため厳密な清浄度が求められます。HEPAフィルターやウルトラクリーナーを搭載した空調設備の導入が必須です。手術室に関しては別途詳細な空調方式を検討する必要があります。
3.3 サーバールーム
24時間運転が可能な個別空調方式: サーバールームでは冷却が途切れないことが重要なため、個別空調方式で常時一定の温度を保つ必要があります。また故障時の室内の温度上昇に伴うサーバーダウンのリスクもあるため、100%の空調負荷を満たす能力の空調機器を2セット設置するなど万全な対策が必須です。
3.4放射線エリア
個別空調方式またはビルマルチエアコンの導入:病院の放射線エリア(例えばCT、MRI、X線室など)は特殊な空調管理が必要です。放射線機器から発生する熱が大きくまた機器によって変わってくるため、単独での対応が出来る個別空調方式が最適です。室外機置場の確保が難しい場合はビルマルチエアコンの導入を検討しましょう。ただし、MRI室や血管造影室などサーバールームが別に設けてある施設に関しては3.3サ-バールームで述べたような点を考慮する必要があります。
3.5透析エリア
低ドラフト型吹き出し口の導入:透析エリアの空調設備は、患者が長時間にわたり寝たままで治療を受ける特性に対応するため、快適性と効率的な温湿度管理が重要です。ドラフト(風の流れ)を感じにくい環境を提供しつつ、厳密な温湿度管理を行うために低ドラフト型吹き出し口(誘引エアビームなど)の採用を検討しましょう。初期費用が比較的高くなる場合がありますが、患者の快適性を求めるためには必要なことですね。
⇒誘引エアビーム【空気式放射整流ユニット(風を感じない吹出口)】(木村工機製)参照はこちら

やっぱり病院って色々なエリアがあって複雑ですね~

これは各病院によっても色々変わるので実態のヒヤリングが必要やで!

病院の担当の方と密に打ち合わせが必要ってことですね!

4. エネルギーコストと長期的な運用管理
4.1 エネルギーコストの長期予測
将来的には、電力とガスの料金が今後変動する可能性があります。電力コストのピーク対策として、昼間の使用を抑える夜間の熱蓄熱システムやガスコージェネレーションシステムなどの導入も検討してもよいでしょう。
4.2 メンテナンスと更新計画
フロン排出抑制法への対応: フロンを使用する冷媒が多い空調設備では、フロン排出抑制法の基準を守るため、定期的な点検と漏えい対策が必要です。
設備の耐用年数: 一般的に、空調設備の耐用年数は15年程度とされますが、ファンコイルやチラーの部品寿命も考慮し、メンテナンスプランを計画することが重要です。ただ、稼働時間の長い空調系統については短いスパンでの更新が考えられますので、それを考慮した空調計画が必要です。

1,熱源と空調方式の検討
2,各エリアごとの検討
3,保守管理に対する検討
この3つの検討が必要ってことですね!

そういうこと!順番に着実に検討していこ!
空調設備の保守契約については下記の記事もご覧ください
5. まとめと提案
これまでの内容をまとめると、以下のポイントが病院の空調設備選定において重要です。
- エネルギー源の多様化とコスト管理:電気とガスを組み合わせることで、エネルギー効率とコストを最適化できます。都市ガスが供給できる場所においては最大電力のピークカットを行うために、一部の系統の熱源をガスにするか、ガスコージェネレーションシステムの導入がおススメです。
- 病院のエリア特性に合わせた空調方式の選択:患者やスタッフの安全性、快適性を第一に考え、用途に応じた空調方式を選ぶ必要があります。部屋の内部発熱などを考慮し、冷房暖房の切替時期を考えて系統の計画をする必要があります。中間期ではこっちの部屋では冷房にしたいのに、あっちの部屋は暖房が…ってことがよく起こります。そうならないために系統を分けたり、個別空調を採用したりする必要があります。
- 長期的な視点での設備維持管理計画:病院ではエリアによって空調の稼働時間が大きく違います。稼働時間の違う部屋を同一系統にしてしまうと、更新する時に無駄になってしまうケースがあります。こういったことが無いよう、設備の更新サイクルを見据えた空調計画と管理が重要です。
病院の空調設備選定には、設備導入にかかる初期コストだけでなく、ランニングコストやエネルギー効率、メンテナンスのしやすさといった長期的な視点も重要です。都市部の医療施設としての特性や将来のエネルギー動向も見据え、最適な空調システムを構築することで、快適かつ安全な医療環境の実現を目指すことが求められます
病院の空調設計の考え方をモデル病院を用いて具体的に解説していますので下記の記事もご参照ください。
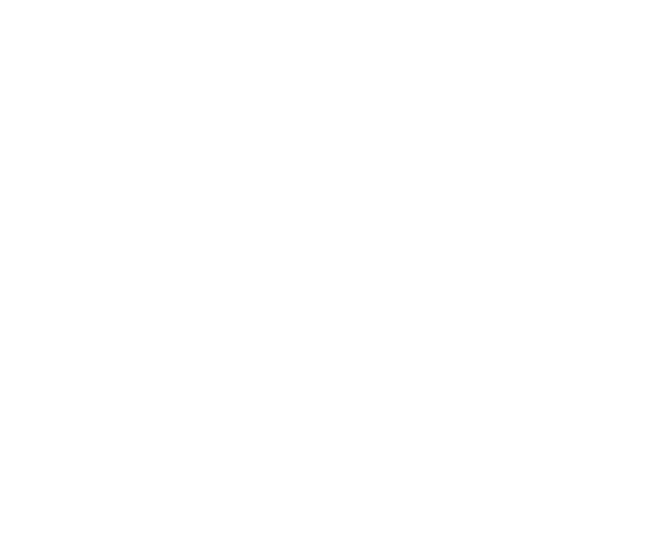







コメント