仕事をしながら資格を取得するって時間の制約もあり大変ですよね…
激務をこなして帰ってきてからの勉強は本当につらいですよね。
また、勉強が久しぶりなのでどのようにすればいいのかも忘れてしまった方も多いのでは…
私のようなアラサーのサラリーマンが本業をこなしつつもこの資格を取得した方法を記事にしています。
この記事を読んでいただくと勉強方法が明確化し、効率よく資格所得が出来るようになると思います。
私、マッチ棒が消防設備士甲種4類の資格の取得をサポートします。
テキストは1冊に絞る!

先輩、消防設備士甲種4類テキストを何冊か買おうと思ってるんですけど、どれがいいですか?

テキストはまず1冊に絞るのが基本やで!
あれこれ手を出すと結局どれも中途半端になるからなぁ

確かにそうですね。それならおススメのテキストあります?

下で紹介しているテキストでいいかな、基礎からわかりやすく解説しているからいいと思うよ。

ところで試験問題ってどんな内容なんですか?

よし!試験内容と合格ラインについて説明するで!
試験の科目と合格ラインを確認!
試験問題は以下のように構成されています。
筆記問題
基礎知識…10問
法令…15問
構造・設備の工事・整備…20問
実技問題
鑑別5問と製図2問の計7問
各科目で40%以上、全体で60%以上の正解率が必要

うわっ、筆記も実技も60%以上が必要って、なかなかハードル高いですね。真剣に勉強します!

まずは一通りテキストに目を通すだけでOK
テキストを進める際、最初にするべきことは筆記試験の全体像を把握すること。
ここで重要なのは、「覚えるべき数字があることを知るだけに留める」こと。
わたしは「この段階では覚える必要はない」と強調しています。
例えば、火災感知器の設置基準や点検周期など、たくさんの数字が出てきますが、この段階ではあくまで「こういう項目があるのか」と理解するだけにとどめておきます。
実技のことは今は忘れて筆記に集中!
当初は実技の勉強は後回しにして筆記試験に集中するのが良いですね。理由はシンプルで、筆記試験の知識がなければ実技の内容は理解できないからです。
筆記の内容を固めてから実技に進むほうが効率的です。
この時点では実技のことは頭から一旦切り離し、筆記試験に集中します。
テキストの問題を解きつつ苦手分野を見つける
筆記試験の各科目に取り組む際、テキストに章ごとの問題がついている場合はこれを活用します。テキストを一通り進める過程で、自分がどの分野に弱点があるのか把握していくのが目的です。

確かに、苦手分野を見つけるのが大事ですね。

各科目で40パーセント以上が最低ラインやからな!

過去問を購入し実践形式で解いて正解率をチェック
筆記の内容が一通り理解できたら、次のステップとして過去問題集を手に入れます。特に、過去5年分の問題集が有効です。過去問を解くことで、出題傾向や自分の理解度を再確認でき、より試験対策が具体的に進められます。
5年前の試験問題を実践形式で解いて正解率をチェックしよう。ここでのポイントは、「実際の試験と同じ時間配分で解く」こと。実際の試験時間に合わせて問題を解くことで、時間配分や回答のペース配分も練習できます。
必ず過去問題集を購入して実践感覚で試験になれることが大切です!
結果に応じたリカバリープランを練る
過去問を解いた結果をもとに、次の学習ステップを考えます。
正解率が30%以下:この場合、基礎知識がまだ十分に身についていない可能性が高いです。テキストに戻り、もう一度内容を読み返して知識の土台をしっかり固めましょう。
正解率が40%から60%:この場合、合格ラインまでもう一息です。テキストで学んだ基礎をノートにまとめ、特に「覚えるべき数値や要点」をピックアップして反復学習します。具体的には、通勤時間や昼休みの隙間時間を活用して、数字や法令の条文などを反復して覚えます。
この段階では、ある程度覚えるべき数字や内容が明確になっているため、ノートにまとめて持ち歩きながら少しずつ頭に入れていきます。

わたしの場合は通勤時間に自分の頭の中で問題出して、あの数字はこうやったな…あれ?あの数字忘れたぁ!となったら会社に着いてから確認したりしたで。」
まとめ
今回はマッチ棒が実践した勉強法をご紹介しました。
本業を頑張りつつも空いた時間を有効活用して勉強すれば、あなたも必ず結果がついて来るはずです。
次のステップでは実技試験のための勉強に挑みますが、それまでにまずは筆記をしっかり固め、総合で60%の正解率になるまで準備を万端に整えましょう!
製図問題が苦手な方はこちらのテキストの購入をおススメします!
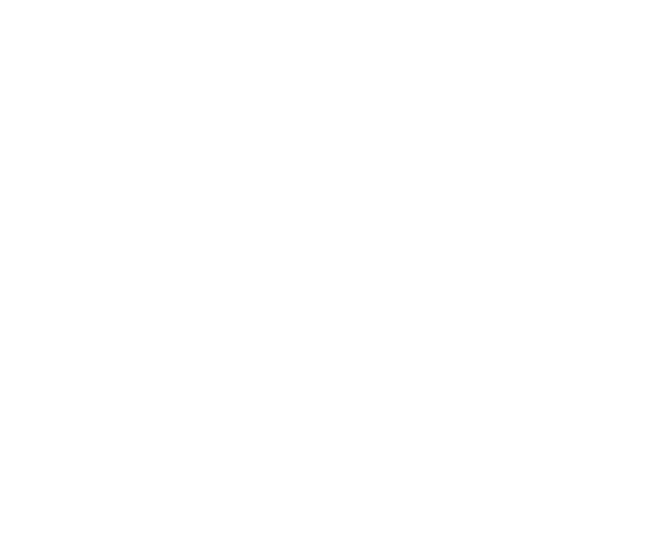









コメント