
昨日本部長から最近光熱費が上がってるから何か削減する方法考えろ!って言われたんですよ~マッチ棒先輩!何かいい方法あったら教えてください。

私はエネルギー管理士を取得して実務経験を積んできたから提案は出来るで!今の時代20,000㎡以上の病院を管理するにはエネルギー管理士は必要な資格やからオイル君も目指してみたらどう?

え~っエネ管ですか?あれ結構難しいでしょ~?僕には無理ちゃうかな~

簡単な資格ではないけど、概要や取得するメリット、試験の難易度や効果的な勉強法についてわかりやすく解説するよ。最後まで聞いてくれたら取得に近づけると思うで!
エネルギー管理士とは?
エネルギー管理士は、企業や施設におけるエネルギーの使用効率を高めるための資格で、国家資格としてその価値が高く認知されています。エネルギー管理士の役割は、エネルギーコスト削減や環境負荷の低減を目的に、省エネルギー計画の立案、実施、そして監督を行うことです。エネルギー管理士は主に「熱管理士」と「電気管理士」の2つに分かれ、それぞれ熱エネルギーの効率化や電力の管理に特化しています。この資格は製造業やビルメンテナンス業界、電力会社など、幅広い分野で需要があります。
エネルギー管理士の活躍する場所は?
エネルギー管理士は、産業界や商業施設、公共施設などのエネルギー管理部門で活躍しています。例えば、大手企業の工場やオフィスビル、ショッピングモール、病院などで省エネ対策の導入や監視、改善を担当します。また、再生可能エネルギーの導入やエネルギーマネジメントシステム(EMS)の開発・運用にも携わることがあり、持続可能な社会の実現に大きく貢献しています。
エネルギー管理士の将来性は?
持続可能な社会の構築が世界的に求められている今、エネルギー管理士の需要は増加しています。企業にとっても省エネ対策は必須であり、エネルギー管理士のスキルを持つ人材は重要な戦略パートナーとなり得ます。また、技術革新によってIoTやAIを活用したエネルギー管理システムが普及する中で、エネルギー管理士の知識と経験がより高く評価されるでしょう。
エネルギー管理士に向いている人は?
エネルギー管理士に向いているのは、論理的思考や分析力を持ち、効率化や改善に興味を持つ人です。さらに、エネルギー使用量の監視や管理に精通するため、継続的に学習し、最新の技術動向に対応する柔軟性が求められます。また、技術的な知識だけでなく、環境への配慮や社会的責任を果たす意識も重要です。

エネルギー管理士についてはよくわかりましたけど、受験資格とかはどうなんですか?

受験資格はなくて誰でも受けられる!次は試験概要と難易度を説明するで!

エネルギー管理士試験の概要とスケジュール【2024年の場合】
2024年のエネルギー管理士試験は、通常年度ごとに開催されます。この試験は、熱管理士と電気管理士の2つに分かれており、どちらかを選択します。それぞれの試験に異なる科目が設定されています。受験資格は特に問われませんが、試験内容は高度な専門知識を要するため、十分な準備が必要です。
試験の概要
エネルギー管理士試験の概要については、次の通りです。
・申込期間(および受験手数料の入金期限)
4月の上旬〜中旬から6月上旬~中旬
2024年は4月5日(金)〜6月19日(水)の期間でした。
・申込方法
郵便又はインターネット
・試験日
7月下旬~8月上旬の日曜日
※ 2024年は8月4日(日)に実施されました
・合格発表
9月中旬〜下旬ごろ発表
(HPで発表。合否通知書も送付)
※ 2024年は9月17日にHPで発表されました
・試験形式
マークシート方式の筆記試験(穴埋め選択問題)
・受験費用
受験料17,000円(非課税)※←結構高い!
※旧制度からの経過措置により、1科目のみの受験は10,000円(非課税)
・受験地
北海道、宮城県、東京都、愛知県、富山県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県
・受験資格
受験資格なし※
※受験資格はありませんが免状取得には取得前後に1年間の実務経験が必須です。
注意:免状の取得には試験に合格+1年間の実務経験が必須となっていますので、試験に合格前後に実務経験を積んでから免状の申請となります。実務経験のない方は合格通知を保管しておく必要があります。
受験科目と試験当日のスケジュール
エネルギー管理士は、熱分野と電気分野の2分野で構成されていて、受験科目や試験当日のスケジュールは下記のようになっています。
基礎区分(熱・電気共通)
科目Ⅰ【必須共通科目エネルギー総合管理及び法規】
・試験時間:80分
・内容:以下のとおり ※()内は問題数
●エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律および命令(1)
●エネルギー総合管理
エネルギー情勢・政策、エネルギー概論(1)
エネルギー管理技術の基礎(1)
専門区分(熱分野)
課目II【熱と流体の流れの基礎】
・試験時間:110分
・内容:以下のとおり ※()内は問題数
●熱力学の基礎(2)
●流体工学の基礎(1)
●伝熱工学の基礎(1)
課目III【燃料と燃焼】
・試験時間:80分
・内容:以下のとおり ※()内は問題数
●燃料及び燃焼管理(2)
●燃焼計算(1)
課目IV【熱利用設備及びその管理】
・試験時間:110分
・内容:以下のとおり ※()内は問題数
●計測及び制御(2)
●熱利用設備
:ボイラ、蒸気輸送・貯蔵装置、蒸気原動機・内燃機関・ガスタービン(2)
:*熱交換器・熱回収装置(1)
:*冷凍・空気調和設備(1)
:*工業炉、熱設備材料(1)
:*蒸留・蒸発・濃縮装置、乾燥装置、乾留・ガス化装置(1)
*印は、4問題中2問題を選択し解答
専門区分(電気分野)
課目II【電気の基礎】
・試験時間:80分
・内容:以下のとおり ※()内は問題数
●電気及び電子理論(1)
●自動制御及び情報処理(1)
●電気計測(1)
課目III【電気設備及び機器】
・試験時間:110分
・内容:以下のとおり ※()内は問題数
●工場配電(2)
●電気機器(2)
課目IV【電力応用】
・試験時間:110分
・内容:以下のとおり ※()内は問題数
●電動力応用(2)
*電気加熱(1)
*電気化学(1)
*照明(1)
*空気調和(1)
*印は、4問題中2問題を選択し解答
基礎区分では熱・電気分野とも共通の【課目I】を、専門区分では熱分野と電気分野それぞれの【課目II】【課目III】【課目IV】を受験します。
各課目とも得点が60%以上で「課目合格」となり、4課目すべてに合格することでエネルギー管理士試験合格となります。
なお、一部の課目のみ「課目合格」となった場合、その試験が行われた年の初めから3年間、合格課目の試験が免除されます。


先ずは【熱分野】か【電気分野】かを選択する必要があるんですね…

そう!出身の学科や実務での経験でどっちが得意かを判断する必要があるな。
エネルギー管理士の合格率と資格難易度
合格率は毎年変動します。全体として、試験の難易度は高く、合格率も低い傾向にあります。
エネルギー管理士の合格率
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 8,586 | 3,175 | 37.0% |
| 2023年 | 8,137 | 3,074 | 37.8% |
| 2022年 | 7,766 | 2,636 | 33.9% |
| 2021年 | 7,684 | 2,454 | 31.9% |
最新のデータによると、エネルギー管理士の合格率は30%台の範囲に収まっています。これは受験者の多くが一定の基礎知識と高度な技術知識を持っていることが前提となっているためです。合格を目指すためには、試験範囲全体を把握し、継続的な学習が欠かせません。
エネルギー管理士は狭き門?
エネルギー管理士は、省エネルギー技術やエネルギーマネジメントに関する高度な知識が求められるため、多くの受験者が難関と感じます。資格取得には専門的な知識の習得に加えて、効率的な学習方法の工夫が必要です。

やっぱり難しそう…先輩…僕には無理ですよ

いや!課目合格を利用して2・3年計画で勉強すれば絶対無理な資格ではないはず!実は私も2課目づつの合格で2年かかったしね…

そうか課目を絞って勉強するのも1つの手ですね.

先ずは課目ⅠとⅡを取ってからⅢとⅣを次の年に取る。予備であと1年って感じかな…でも受験費用が結構高いからなるべく早く取りたいけどな~

エネルギー管理士の勉強方法【熱分野・電気分野】
エネルギー管理士試験の勉強方法には、熱分野と電気分野の特性を考慮したアプローチが効果的です。
熱分野
熱分野では、熱力学や伝熱、燃焼に関する基本的な理論を理解することが重要です。これに加えて、実際の設備や機器の操作方法や効率改善方法に関する知識も必要です。計算問題が多く出題されるため、公式を覚えただけでなく、実践的な計算力を鍛えることが求められます。
電気分野
電気分野では、電気回路や配電システム、電力消費量の計算方法について学ぶ必要があります。特に、エネルギー使用の効率化を図るために、負荷管理や省エネルギー対策の知識が試されるため、現場で活かせる知識と技術を身につけることが大切です。
勉強時間の目安
合格に必要な勉強時間の目安はどうれくらい?
経験者と未経験者では、かなり違ってきますが、未経験から合格を目指す方の場合は、基礎を勉強しながら過去問に取り組んでいく必要があるので、600時間程度必要でしょう。
エネルギー管理士の試験は出題範囲が広いので週20時間(平日2時間×5日、休日5時間×2日)勉強するとして、30週間(7か月弱)は必要になってきます。
なお、大学や工業高校で電気や熱の専門分野を勉強していた経験があれば、すでに基礎知識があるので、20週間(5カ月弱)くらいになると思います。
またテキストばかりを勉強していても絶対に合格は無理です。過去問題集(10年分)を必ずやりましょう!これは経験で感じたんですが、過去問を早めに経験して今テキストで勉強している内容で本当に大丈夫なのかを確認していく必要があると思います。
テキストで勉強!→過去問!→テキストで勉強!→過去問!の繰り返しが必要です。
必ず過去問を解くことが大事です!
私が実際に使用していた過去問題集はこちら

一発合格は無理っぽいので2年計画で挑んでみることにします!半年前から3課目勉強して最低2課目合格を目指す!そして次の年は2課目に絞って勉強して…

おお~そんな感じそんな感じ!それと必ず過去問をやり込むのも忘れたらあかんで!

わかりました!頑張ります!

すぐやる気になってくれたのはいいけど、モチベーション維持するが大事なんでちょこちょこ様子見ていかなあかんやろね(^^)

まとめ
エネルギー管理士資格は、高度なエネルギー管理技術を持つ専門家として企業や社会に貢献できるだけでなく、キャリアの幅を広げる強力な資格です。資格取得には難易度が伴いますが、効率的な学習と専門知識の習得によって、確実に挑戦する価値がある資格と言えます!
皆さん頑張ってください! ではまた!!
省エネルギー法についてお調べの方は下記の記事を参照下さい。
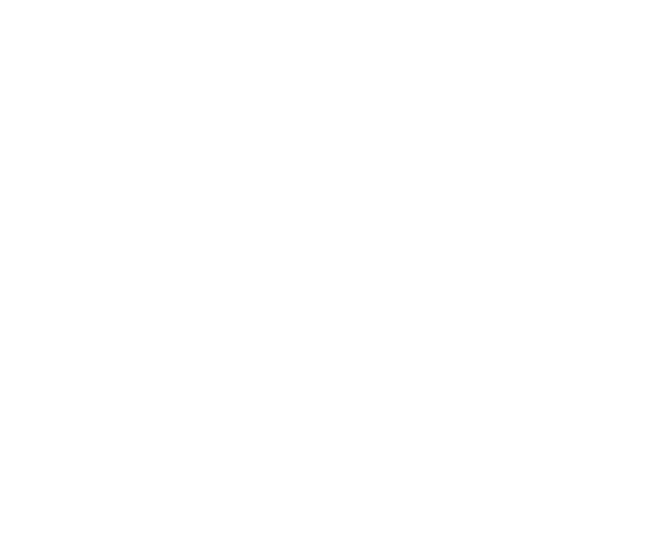
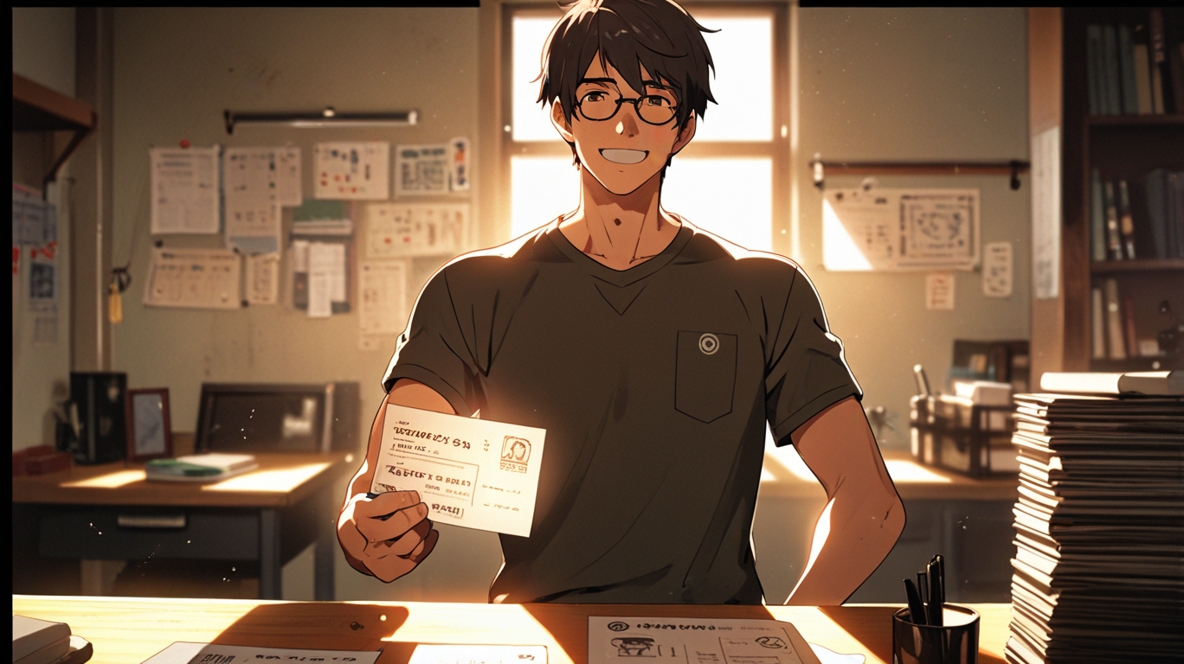








コメント